卓話時間
第1296例会
2006年06月19日 (月曜日)
- タイトル :
- ゲスト卓話
「頼 山陽とその周辺」
- 卓話者 :
- 作家 見延典子 氏
一昨年(2004)十月から、中国新聞に連載を続けている小説『頼山陽』はおかげ様で四百回を越えた。
頼山陽といえば、『日本外史』を著した博学者として、固いイメージがあるが、私の小説では「江戸時代を生きた現代人」と想定し、既成の概念にとらわれない自由人、自らの「欲望」に忠実に生きる人物として描いている。
すでに四百回を越えていることから、これまでの内容の全てを振り返るのは時間的に無理であり、今回は『日本外史』を中心に述べていきたい。
そもそも『日本外史』とは、源平の時代に始まる武家の興亡を、山陽が生きた時代、つまり徳川第十一代将軍家斎の時代まで、六百年にわたって綴ったものである。
歴史書とはいわれているが、誤りも多く、というより山陽自身、内容を面白くするため脚色を加えたところがあって、今日では歴史小説という評価が定着している。
現在も岩波文庫に収められるし、口語訳も出版されているが、漢文教育を熱心に受けてこなかった世代には大変読みにくく、なぜ幕末ベストセラーとなったのか理解しにくい面もあろう。
この点については江戸時代の事情を考えねばならない。現代でこそ歴史書は手軽に入手し、読むことができるが、当時は徳川家に対して発言することは禁じられており、歴史書を書くことは禁忌に触れる危険もあったことから、多くの学者は二の足を踏んでいた。仮に書いたとしても、当たり障りのない内容であった。
六百年にわたる通史を書いた山陽が、どれほど勇気があったのか、おわかりいただけよう。
但し、『日本外史』は山陽の生前は出版されなかった。費用の問題もあろうが、公刊されるまでには各方面の理解を得る必要があったためだろう。
ところで『日本外史』は尊皇論が基盤となっている。そのため山陽は尊皇家と呼ばれる。
現代的感覚からいうと、尊皇論にはナショナリズムに結びつく考えがあると受け取る傾向があるが、江戸時代、尊皇論は徳川家も容認しており、その意味では最も安全な考え方であった。
しかし安全な中にも、反幕的な思いも隠れている。それは徳川家の主流派、反主流派の対立があったからだ。ここに山陽が後世、評価を変えられていく萌芽が潜んでいる。
山陽の死後、時代が加速度的に変わり、幕末には尊皇攘夷が叫ばれ、息子の三樹三郎は安政の大獄で刑死した。
山陽にとっては想像もしていないことだったろう。
しかも王政復古後、明治政府の政権を固める支柱となったものが、『日本外史』とあわせて書かれた『日本政記』であったことを考えると、山陽の思想は軍部によって都合のよいように利用された。
明治時代、広島には大本営が置かれ、臨時議会も開かれた。広島は軍部であった。
山陽が理想とした国家が、このような形のものであったとはとうてい考えられない。
誰が歴史を、いや、山陽を歪めてしまったのかが、私の小説の後半の大きなテーマである。
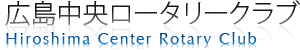

 広島中央ロータリークラブ 事務局広島市中区基町6-78リーガロイヤルホテル広島13F
広島中央ロータリークラブ 事務局広島市中区基町6-78リーガロイヤルホテル広島13F